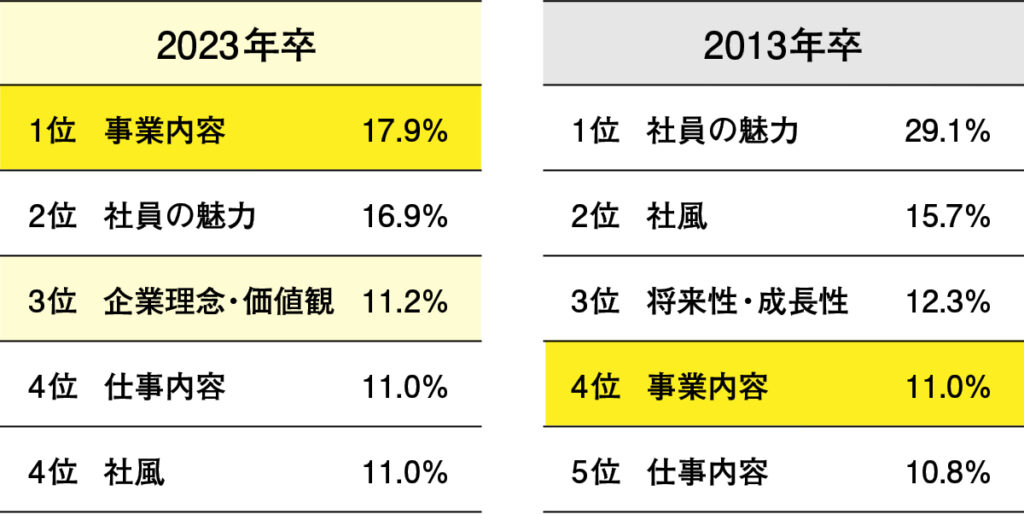2023年も折り返し、7月に入りました。
リクルートの調査によると、2024年卒の内定率は7月1日の段階で83.2%。
6月までは前年よりも高い数値が続いており、
新卒採用の早期化が進んでいることがうかがえましたが、
7月は前年と同水準になっています。
引き続き、売り手市場は続いていますから、
「応募がこない」「内定を辞退されてしまった」など、
厳しい状況に置かれている企業も多いのではないでしょうか。
株式会社学情が人事担当者を対象におこなった調査では、
2024年卒採用について「採用難易度が高い」とした企業が8割を超えています。
「プレエントリー数も、選考参加者数も、前年より大きく減っている」
「既に複数の内々定を持っている学生が多く、内々定を出しても承諾に至らない」
などのコメントが紹介されていました。
新卒が採用できないという企業が増える中、
既卒や第二新卒など20代を対象にした、
いわば「20代通年採用」が広まってきています。
株式会社学情の調査では、「20代通年採用」を
「既に実施している」と回答した企業が半数以上にのぼっており、
「検討している」と回答した企業と合わせると、
7割以上が「20代通年採用」に前向きです。
20代に限らず、経験者採用の割合を増やす企業は増えてきており、
別の調査では、「経験者採用の人数を、前年度より増やす予定」と
回答した企業が約4割。
新卒採用と経験者採用の割合で見ると、
「5:5」にする企業が最も多くなっています。
以前のブログでも、新卒通年採用の可能性について触れましたが、
既卒や第二新卒に対象を広げた通年採用は、
人材確保のための有力な施策として、検討する価値があると思います。
ちなみにですが、今は「中途採用」ではなく
「経験者採用」と呼ぶのが一般的になってきています。
経団連は、転職者などの採用で使われることが多い
「中途採用」の呼称を「経験者採用」に改める方針なので、
採用活動の場面でも「経験者採用」を使用するのが良いでしょう。
また、このような流れのなかで、
中小企業にとっては新卒採用のチャンスが増えているという見方もできます。
学生にとっては、新卒で入社した企業は
「社会人としての“いろは”を学ぶ場」でもあるので、
ある程度の教育体制が整っている必要はありますが、
中小企業ならではの機動力や担当業務の幅広さを
魅力的に感じる学生もいるはずです。
自社ならではの良さを生かし、選ばれる理由をつくっていくことが大切です。
採用市場は日に日に変化しています。
「新卒採用」「経験者採用」という区別が
時代遅れになる日も近いかもしれませんね。
国も労働力の流動性を高める施策を取っていますし、
今後さらに採用も多様化していくでしょう。
これは自然な流れです。
日本全体の競争力を考えても、流動性は高める必要があります。
起こった変化に対応するのは大変に感じますが、
「変化はどんどん起これば良い」というくらいの姿勢で、
積極的に変化していきましょう。
私たちグロウプスは、採用コンサルや採用ブランディングを通して
福井県の企業様の採用力向上のお手伝いをさせていただいています。
これからも採用やブランドづくりに役立つ情報を
発信していきたいと考えています。
弊社にご興味がある方はぜひホームページをご覧ください。
<参考>
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001053.000013485.html